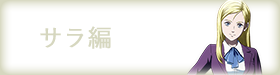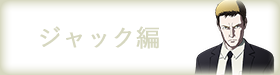----------------------------------------
⑤:『新たな道標』
----------------------------------------
そうして過ごしていく内、月日は飛ぶように過ぎ――、
入社から3年が過ぎたある日、私は上司から呼び出された。
「――中国出張、ですか?」
そう問い返す私に、研究所の上司は頷いた。
彼はさほどXM研究に情熱を持っていない、官僚的な中国人男性だった。人柄は温厚で、私の問いにもにこやかに答える人だった。
「そう、中国本社の上層部も、君に興味を持っていてね。一度本社に顔を出して欲しいとの事なんだ」
「……被験体である私が東京を離れると、研究が滞りますが……」
「それは判るが、君も入社以来3年間、ずっと働き詰めだろう? 休養も兼ねて、少し外の空気を吸って来たらどうかな?」
言われてみれば、確かにその通りだった。
XM研究者となってから、仕事ばかりの日々を送ってきた。XMの秘密を解明する使命感に煽られて、研究以外の事は何もしてこなかった。
だけどようやくそれも少し実を結び、自分の特質も制御できるようになった。これを機に外の世界が、私の眼にどんな風に映るのかを、確かめてみるのも悪くない。
(それにヒューロンの本社で、どんな研究が行われてるのも気になるし……研究者としての見識を深める、いい経験になりそう)
「わかりました。謹んでお引き受けします」
「おや、急に表情が明るくなったね。『研究者として良い経験になりそう』と思い直したかな?」
「鋭いですね。顏に出てましたか?」
「なぁに、実は私もセンシティブでね。XMの力により、人の心を読む力を発揮できるのさ」
上司の冗談に私は笑う。研究所では、この手のジョークが流行っていた。何か想定外の事があると、なんでも『XMの力』という事にしてしまうのだ。
それはあくまで冗談だ。いかにセンシティブと言えど、人の心が読めるなんてありえない
「さて、そうと決まれば本社に伝えておこう。『貴重な被験体サラ嬢がそちらに向かう、厳重な警備体制を頼む』とね」
「そんな大ごとにしなくても結構ですけど……」
「いやいや、大事な職員である事は事実じゃないか。本社には警備部もあるし、ちょうどいい。現地の案内も彼らに頼めばいいさ」
私は上司の申し出を、素直に受ける事にした。
それに本音を言えば、こうして会社に大切に扱われる事は、そう悪い気分ではなかった。ずっとこの世に居場所がないと思っていた私も、ようやく居場所を手に入れられた気がした。
一生懸命頑張っていれば、道は開ける。勇気を出して歩き出せば、新たな世界が広がる。
(中国ではどんな出会いが待っているのかな……? 少し楽しみになってきた)
私は期待に胸を膨らませ、出発の日を待つ事にした。
『全てが上手く行っている』と、愚かにも思いながら――。