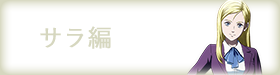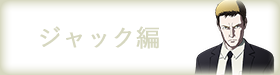----------------------------------------
③:『翠川誠の追憶』
----------------------------------------
警視庁を出ると、外はすっかり夕闇に沈んでいた。
桜田門駅から地下鉄に乗り込み、まっすぐ自宅に向かう。
『用事がある』と言ったのは嘘じゃない。今夜は僕のやっているオンラインゲームの、ギルド対抗戦が行われるのだ。
僕的には大事な用事なのだけど、警部に行ってもまず理解されないだろうから、その辺は適当に濁したという訳だ。
自宅最寄りの駅で地下鉄を降り、コンビニでおにぎりを買って、家路を急ぐ。
ボロマンションの階段を駆け上がり、ようやく自宅に辿り着いた。
「はぁ、疲れた……あんなに人に会ったのなんて、久しぶりだしな……」
そうつぶやきながら、電気のスイッチを入れると、「我が家」が浮かび上がった。
地味で窮屈だけど、世界一落ち着く僕の家。椅子に腰かけながら、PCのスイッチを入れる。
PCが起動するのを待ちながら、僕は自分の手を見つめた。能力の暴発を防ぐ為の、革手袋に包まれた右手を。
(これからこの『力』を、仕事に使うのか……事件の捜査依頼が来るたびに……)
そう考えると、背筋に冷や汗が滲む。心音が高まり、呼吸が荒くなってくる。
脳裏に、次々と嫌な記憶がよぎる。それはこの能力によって、悩まされてきた記憶だった。
――『物の記憶を読む能力』は、生まれつきのものだった。
物心ついた時には既に、その能力は身についていた。
いや、身に着いたというのは正確ではないかもしれない。
僕自身の意志に関わらず、右手に触れた物の記憶が、脳裏に流れ込んで来ていたのだ。
小さい頃は、それが当たり前の事だと思っていた。
僕だけじゃなくて、他の皆も、同じように持っている力なのだと。
だから僕は考え無しに、そうして読んだ記憶を、両親や友達に語った。
だけどそうする度に周りは、僕を奇妙な目で見るようになっていった。
両親はそれでも、僕を『ちょっとおかしな力を持った子供』として、大事に育てようとしていたのだろう。
だけど誰だって、他人に見られたくない部分がある。
あれは6歳の頃だったろうか。僕は誕生日のお祝いに、両親と一緒に街に出た。
僕は何気なく、母と手を繋ごうとした。だけどその瞬間、母が目の色を変え、僕の手を払いのけたのだ。
僕は驚き、母の顔を見た。その時の母の表情を、僕は忘れる事はないだろう。
そこには、何か不気味なものを見る目が――得体の知れない何かに怯える表情が浮かんでいたのだ。
その日を境に、僕は少しずつこの力が、異様なものなのだという事に気づき始めた。
だけど気づくのが少し遅かった。
その頃には既に両親だけじゃなく、周りの大人も友達も、僕の力に気づいていた。
『誠は普通じゃない』
『触られると頭の中を読まれるぞ』
『なんなんだよ、その右手』
『近寄るな、あっち行けよ』
『気持ち悪いんだよ、お前』
友達からそんな言葉を浴びせられるようになって、僕はようやく悟った。
僕は他人に触れる事も、近づく事も許されない存在なのだと。
もちろん望んでこんな力を持って、生まれた訳じゃない。
それに僕が読めるのは、あくまで『物の記憶』だけだ。人が考えている事は判らないし、過去の記憶を探る事も出来ない。
だけどそんな事は、周りから見ればどうでもいい事だった。僕は家でも学校でも、明らかに異質な存在だった。
やがて僕は、他人との関わりを諦めた。
そして直接他人と触れずに済む、インターネットの世界に安らぎを見出した。
仕事も遊びも人づきあいも、全てPCがあれば事足りる。
そうやって僕を拒絶する世界と、なんとか折り合いをつけていこうと思ったのに――。
(わざわざその世界に出て、自ら『外界』に触れろと……? この、呪いみたいな力を使って……?)
それを考えると、胸が締めつけられるようだった。
僕は現実を一時でも忘れようと、オンラインゲームを起動した。