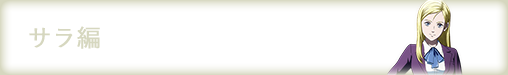----------------------------------------
④:『追憶』
----------------------------------------
――俺は5年前まで、傭兵として戦地を転々としていた。
パキスタン、イラク、レバノン、リビア。求められる戦場があれば、どこにでも赴いた。
別に好き好んで、戦争屋になった訳じゃない。だが俺にはそれ以外に出来る事がなかったし、幸か不幸かセンシティブとしての『才能』があった。それが俺に、そういう生き方を選ばせたのだ。
当時の俺はXMの存在を知らず、自分がセンシティブであるという自覚もなかった。フラッシュフォワードのルールも――つまり青のフィールドの中でのみ、先読みの力が発現するという事も――まだ正確には理解していなかった。だがそれでも戦場を生き抜く為には、十二分に役に立った。
能力の詳細こそ隠していたが、それでも俺はどこの戦場でも重宝された。俺の能力は、自分の命だけではなく、仲間の命を護る武器にもなった。
そんな俺を、部隊の守護神のように慕う者もいた。上官たちは俺を有用な駒として、前線に投入した。長年そんな日々を続け、俺の精神は徐々に擦り減っていった。
戦場で『未来が見える』という事は、何度も自分と仲間が死ぬ光景を見るという事だ。銃弾を頭に喰らってくたばる俺、ロケット弾を撃ち込まれて粉々になる俺、火炎放射器で焼かれて死ぬ俺――俺は自分の死に様についての、ありとあらゆるバリエーションを見てきた。生々しい実感と共に。
戦場で不敗を誇ろうと、俺は駒の一つに過ぎなかった。俺は嫌気が差していた。金と権力欲の為に、戦争を繰り返す政治屋どもにも。それに踊らされるだけの自分にも。だが生き方を変えるには、歳を取り過ぎていた。俺は戦場で命を終えるのだろう。何度も見てきた未来の通りに。
ずっとそう思っていた。あの日、ブラントと出会うまでは。
――その日の事を、俺は今でもよく覚えている。
今から5年前、2013年の初頭。所属していた民間軍事会社を通じて、とある科学者を警護して欲しいとの依頼が来た。
傭兵が要人警護の依頼を受ける事自体は、そう珍しい事ではない。奇妙だったのはクライアントが、俺を名指しで依頼してきた事だ。
俺は傭兵の世界では、多少の有名人だったかも知れないが、一般世間に知られる存在ではない。だが、その科学者は、わざわざ俺を指名してきた。
俺はそこに、わずかな興味と懐疑を覚えた。クライアントの真意を確かめる為にも、そのクリストファー・ブラントという男に会いに行ったのだ。